こんにちは、すだおです。
「品管目線でゆるっと簡単仕事術」では、品質管理目線のビジネススキルや手法
読書で学んだビジネススキルや投資術に関する情報発信もしていきます。
なぜなぜ分析?名前だけ見ると簡単そうだけど、とても深い手法です。
対策を打ったのに改善されない…なんてことはないでしょうか。
トヨタのカイゼンの肝にもなっているこの「なぜなぜ分析」
今回はこのテーマについて簡単に説明したいと思います。
なぜなぜ分析とは
なぜなぜ分析とは、トヨタ生産方式の一つです。
発生した事象の原因を洗い出す方法で、問題の再発を防止、また不具合分析に使われる手法です。
なぜなぜ分析の進め方
事象に対して、現場・現物・現実をしっかり見ながら「なぜ?」「なぜ?」「なぜ?」と繰り返し原因を追求します。
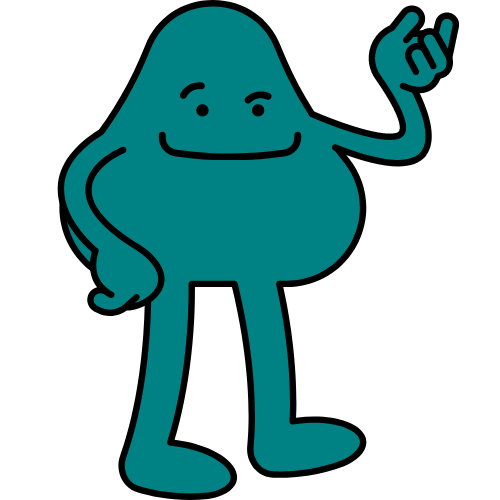
進め方はとっても簡単!名前のとおりだよ
「なぜ?」を5回繰り返すということをよく聞きますが、原因を究明することが目的です。
回数にこだわる必要はなくて、3回でも7回でも問題はありません。
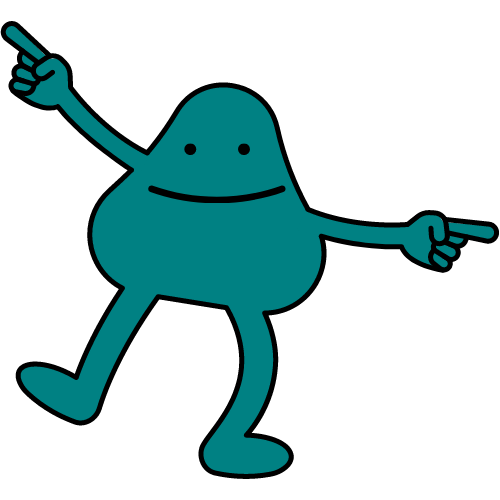
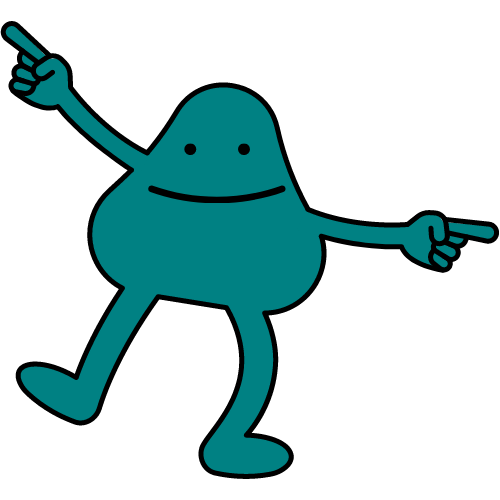
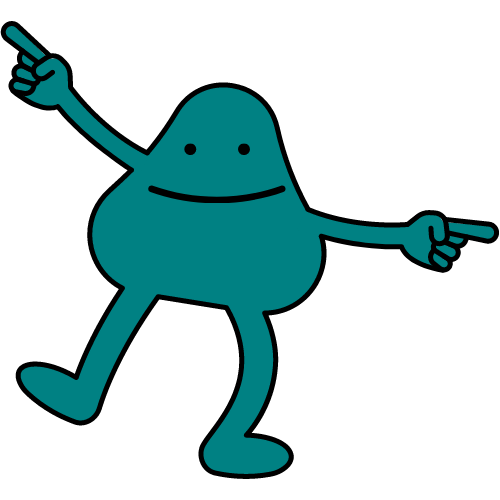
何回でも問題はないけど、「決めつけ」や「論点のズレ」
が発生を防ぐためにも5回ぐらいがちょうど良いかな!
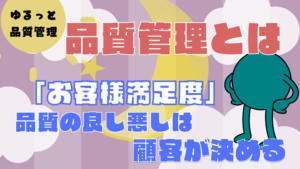
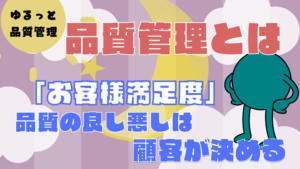
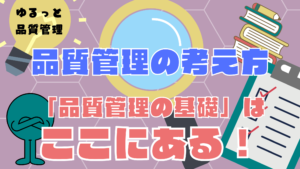
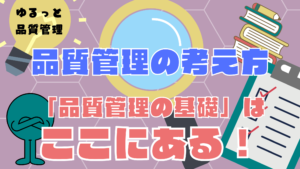
なぜなぜ分析の例
つぎの例を見て現場は改善できるでしょうか。
現場で工員が転倒した
↳(なぜ転倒した?)足を滑らせた
↳(なぜ足を滑らせた)不注意だった
対策 工員に注意する、注意喚起する
確かに注意喚起すると一時的に改善されたように見えるかもしれません。
ただし、人には慣れがありますので、気が抜けた頃に再発することでしょう。
不注意=原因ではなく、不注意は一つの要因だと考えられます。
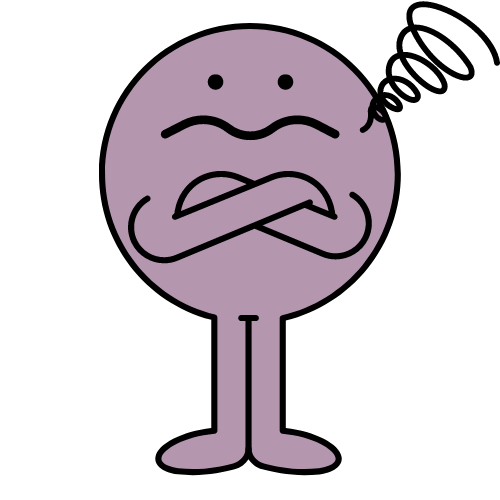
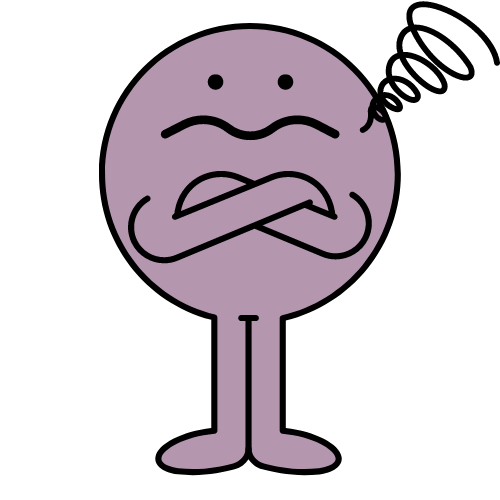
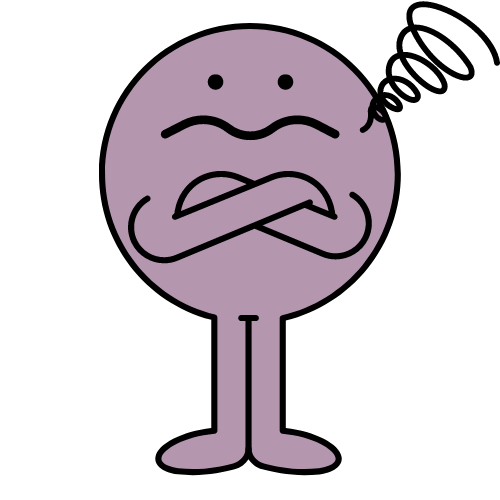
じゃあ、どうしたらいいんだろう…
現場で工員が転倒した
↳(なぜ転倒した?)足を滑らせた
↳(なぜ足を滑らせた?)床に油がこぼれていた
↳(なぜ油がこぼれていた?)フォークリフトから油が漏れていた
↳(なぜフォークリフトから油が漏れていた?)バルブ内のOリングが経年劣化で割れていた
↳(なぜOリングが割れていた?)定期点検を怠っていた
対策 定期点検を行う仕組みを整える
もしくは定期検査を自社ではなく専門業者に検査を委託する
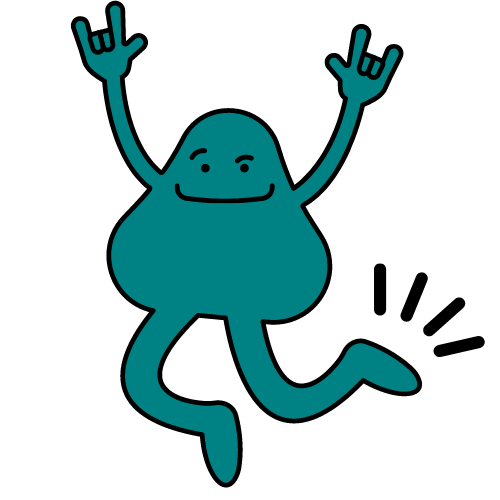
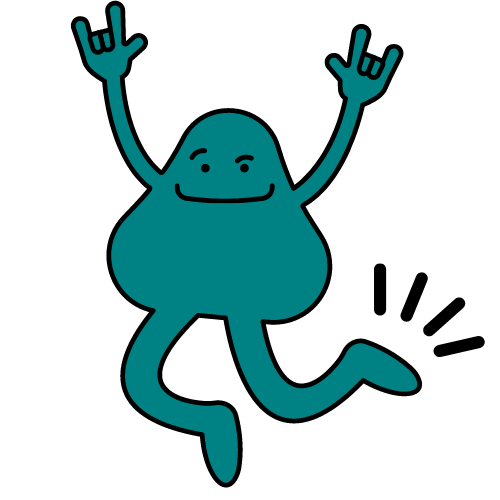
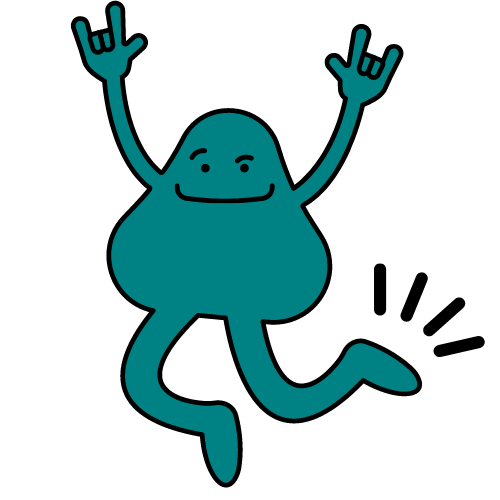
こうしてみると、どうなっただろう!
- 現実、現場を確認することで油に気が付いた
- 現物からフォークリフト→バルブ内のOリングの割れに気が付いた
- そのことでどこの仕組みを変えないといけないかに気が付けた
それにしたがって対策を打てば、再発を防げる改善につながります。
もちろん始めに例で出した、注意喚起等の対策を同時に行うことも良いでしょう。
ポイント・注意点
- 誰かのミスではなく、起こったことに注目し、仕組みやプロセスの改善に繋げる
➡日本人は特に自分を攻めてしまったりもするので注意が必要です。 - 人に対して原因を探しに行くと人が変わるとまた同じ問題が発生する
➡言語化し標準化が必要となります。 - 仕組みやプロセスを守ることが目的になってしまうと、省けるプロセスがあっても変化させることができない
➡無駄な作業が増え、ロスだけが増えてしまうことがあります。 - 途中で、勘や思いつきが入ってしまうと改善できなくなってしまう
➡現場・現物・現実を意識し取り組むことが重要です。 - 複合要因が重なった問題も多いので、対策は複数になることもある
➡一つの要因だけを見てしまうとせっかく対策を売ったのに改善しないなぁなんてことも
なぜなぜ分析のメリット
なぜなぜ分析をするうえでの最大のメリットは次の3つではないでしょうか。
- 問題の真因を見つけれる
- 真因から根本的な解決に導くことができる
- 難しい理論は必要ないので、気軽に着手できる
まとめ
なぜなぜ分析は、生産の場だけでなくあらゆる仕事に利用できる分析ツールといえます。
成果を出している人は自然とやっていることなのではないでしょうか。
始めは手間に感じることもあると思いますが、きっと効率の良い仕組みを作り上げることが出来るはず。
業務を処理することだけを考えると応急処置だけでストップしてしまうことが多いですが、
時間をかけてでも原因を見つけることで再発防止対策が打て、結果的にロスを減らし利益につながります。
品質管理だけではなく他の仕事にも利用できるので、ぜひ仕事の中に導入してみてください。
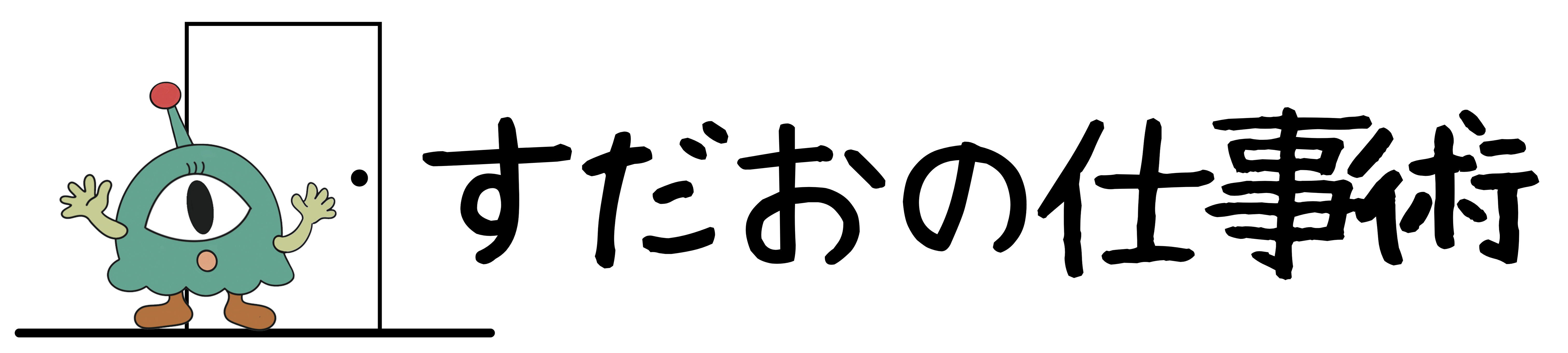
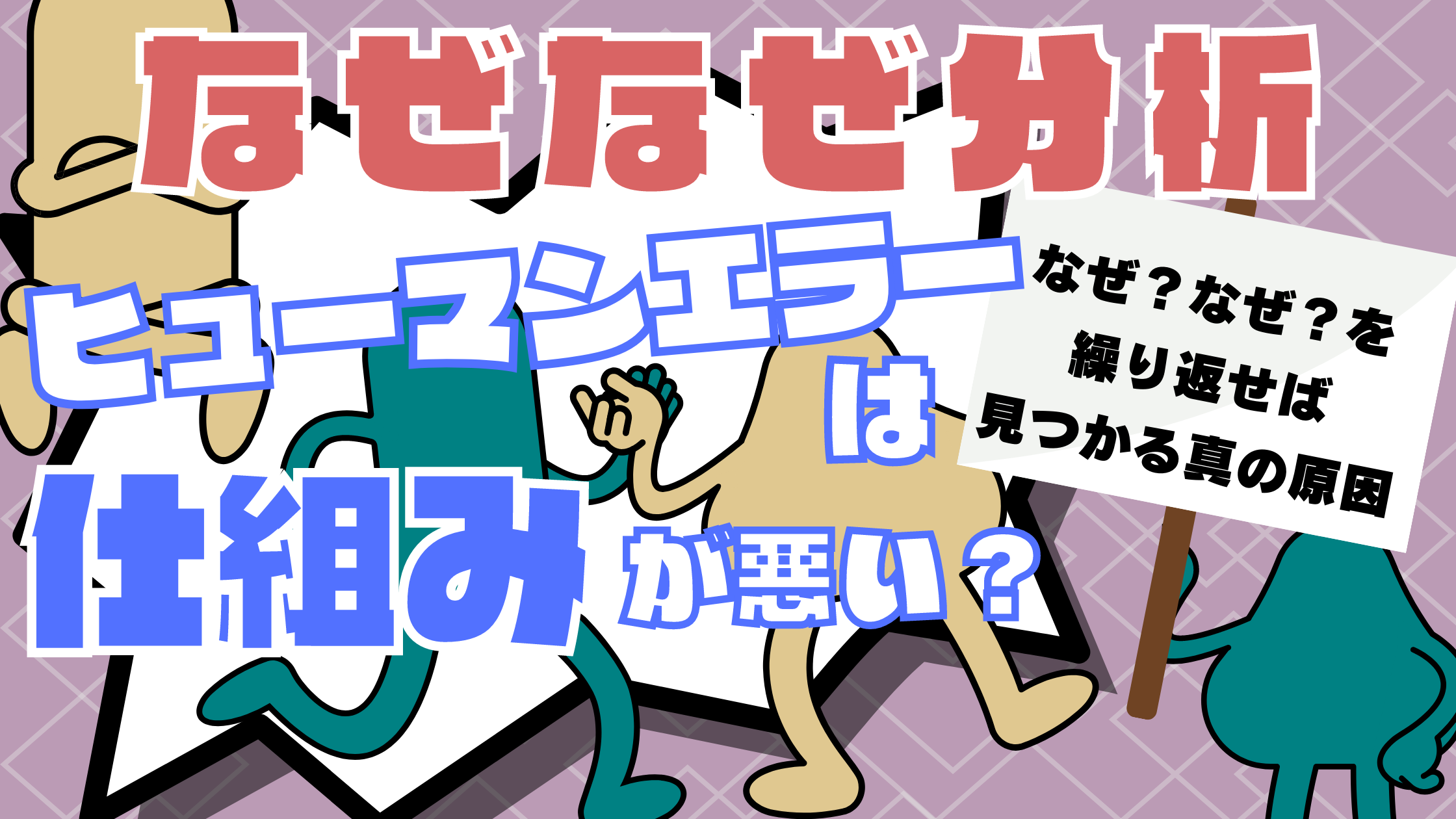
コメント